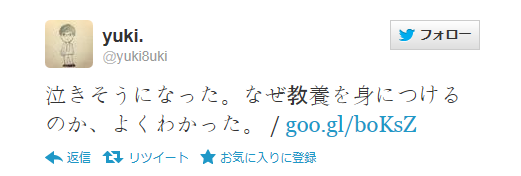読書猿Classic: between / beyond readers
2012.06.03 家庭環境と読書の習慣のこと/図書館となら、できること
http://readingmonkey.blog45.fc2.com/blog-entry-591.html
少女:先生のお父様は、最初大工さんで、そのあと本を修理する職人さんになられたのでしたね。
司書:ええ。
少女:お母様はどういう方ですか?
司書:元気な人です。子供たちの釣りに〈引率〉を口実に着いてきて、一番夢中になって釣りを楽しむような人でした。
少女:やっぱり本が好きな方でしたか?
司書:いいえ。彼女は本を読めませんでした。おそらく自分の名前以外は書くこともできなかったと思います。彼女は早くに父親を亡くして、働きに出なければならなかった母親のかわりに、弟や妹たちの世話をしなければなりませんでした。学校は好きでしたが、ほとんど通えなかったと言っていました。
少女:そうだったんですか。
司書:彼女が読むようになったのは、私の父が亡くなってからです。識字教室を探してきて、そこで読むことを学び始めました。「これでやっとお父さんの仕事を読むことができるね」と喜んでいました。もっとも父は洋古書の修繕を依頼されることが多くて、中身は日本語でないことが多かったのですが。それでも彼女はアルファベットを学んで、一文字ずつ父が残した本を読み始めました。
少女:本で囲まれたお家で成長されたのかと思っていました。
司書:父の仕事の本はありましたが、かえって自分たちが読むものではないという思いがあったのかもしれません。
少女:じゃあ、先生はいつから読むことを始めたんですか?
司書:そうですね。読書の習慣が身についたのは随分後になってからです。
少女:そうなんですか?
司書:両親は私が大学に進むのに反対しませんでしたが、そのためにどうすればいいかは知りませんでした。私たちの周囲にちゃんと勉強したことがある人はいませんでした。後になって思うと、〈勉強の仕方〉が分からないというより、〈勉強すること〉がどういうことなのか分かっていなかったのかもしれません。見よう見まねのやり方をいろいろ試してみたのですが、うまくいっているのかいないのか判断のしようがありませんでした。
少女:それで大学には?
司書:ひとつ合格したところがあったのでそこへ行きました。
少女:そこで図書館の勉強をされたんですか?
司書:いいえ。私が進んだのは哲学の勉強をするところでした。社会によっては高い尊敬を受ける学問であり、それを学ぶところも難関であることが多いのですが、日本ではそうではありませんでした。私にとっては幸運でした。
少女:どうして哲学だったんですか?
司書:何を学びたいのか分からず、何を学ぶべきか決めることもできなかったのです。哲学ならどこへ進めばいいか分からない人間でも受け入れてくれるのではないか、と期待したのだと思います。
少女:そういえば、すべての学問は哲学から分かれてできたって聞いたことあります。
司書:現代では、哲学もまた、多くの学問の母胎である営みから別れ出たひとつの支流であるのですが。そうした学問の事情も、当時は何も知りませんでした。
少女:何だか、今からだと想像もできないですね。
司書:さきほどの質問に答えるのに、あの出会いについてお話するのがよいかもしれません。
大学に入って最初の年、私はできるだけ多くの講義に足を運びました。すべてに興味を感じた訳ではなかったのですが、学びたい何かを見つけるのに、その時はそれ以外のやり方を思いつけませんでした。
あとで聞くと、成績に関してとても厳しいせいで出席者の半分は単位登録しないモグリの学生たちだったそうですが、大きな講義室が学生でいっぱいになる人気の講義がありました。
その最初の日でした。
やってきた老教授は、そのまま無言でチョークをつかみ、ものすごい速さで50余りの文献を黒板に書き上げました。
しばらく呆気にとられる間があって、学生たちがそれをノートに書き写す音が続きました。
しかし圧巻はその後でした。
老教授はひとつひとつ、それらの文献の解説を始めたのですが、一つの文献につき1〜2分間という時間なのに、どれも心の底から読みたいと思わせる紹介だったのです。
最後に教授はこう付け加えました。
「以上がこの講義が前提とする文献である。では、よき週末を」
私は事務室で教授の講義のない時間を確認して、教授の研究室に向かいました。
文献紹介ですらああなのだから、次回以降に行われる講義は大変魅力的なものに感じられましたが、あれらの文献を読む力は、どう考えても自分にはないように思えました。
私はすでにその講義を登録していましたが、理由を話して講義を取ることを辞めようと考えました。
しかし、何度行っても、教授は研究室にいませんでした。
私はあきらめて、とにかくノートに書き取った文献を見てみようと大学の図書館へ向かいました。
図書館の本棚に、教授が書き上げた文献はひとつもありませんでした。
しかし私はそのとき何かに憑かれていたのか、あるいは魔法か何かにかかっていたのでしょう。
つまり、この件について諦めることを、すでに諦めていたのです。
私は生まれて初めて図書館のレファレンスカウンターへ行き、教授があげた文献のタイトルを告げて、見つからなくて困っていると話しました。
目録カードやその他いろいろの検索手段を説明してもらい、かなり時間はかかりましたが、ようやくある選集の中に、文献のひとつが収録されていることを突き止めました。
私の通った大学の図書館は、学生が書庫に入るのは面倒な手続が必要でした。
書庫の存在を知らない学生も大勢いましたが、私もその一人でした。
何とか書庫に入り、移動式書架の間で迷いながら、とうとう目当ての書物がある棚にたどり着きました。
背表紙のタイトルを確認して本を開き、ページをめくっていると、その先に人が立っているのに気付きました。
「ようこそ」
静かで厳かな、しかし熱を帯びた声がしました。
「たくさんの学生が講義を聞きに来るが、ここまで来る者は少ない。本を取りたまえ。探索はまだはじまったところだ」
「あの、ひょっとして……」
「なにかね?」
「教授は講義の度に、こうして書庫で、講義であげた本がある棚の前で待っているのですか?」
「不思議かね?」
「いえ、あの、大変だなと……」
「私は講義以外の時間のほとんどをここで過ごす。ここが私の仕事場だ」
「でも、別に研究室が……」
「あそこはただの事務室(オフィス)だ。電話番でもいれば足りる。それに書物を私室に囲い込むなど愚かだとは思わんかね?」
「あの、そうですか……?」
「この大学にも、構内にあるのに図書館目録に載ってない私蔵本が腐るほどある。大抵の教員の所蔵書は記憶しているから、必要なものがあれば尋ねたまえ」
「はい、あの……ありがとうございます」
「図書館を使い尽くさないようでは大学に来た甲斐がない」
「……あの、質問してもよろしいでしょうか?」
「無論だ。〈使い尽くす〉ものの中には教員も含まれる」
「私は、その、本を読むのが得意ではありません。読書の習慣を持たずに、これまで来ました。正直、教授が挙げられた文献を読む通す力が自分にあるとは思えません。あ、あの……どうすれば本を読めるようになるでしょうか?」
顔から火が出るような恥ずかしさでしたが、それよりも尋ねたいことが言葉になって口から出たのが驚きでした。
今ここでこの人に質問しないと、一生涯、この問いを口にすることがないだろうと思えたのです。
時間にすれば数秒でしたが、教授が口を開くまでの時間は、1日の長さに思えました。
「ついてきたまえ」
「読むことのできない書物は存在しない。読むことをあきらめる読書家がいるだけだ」
「え?あの……」
「一度読み始めたら、眠りに着くまで本を離してはならない。どこへ行くときも持って行きたまえ。もちろん寝床にもだ。横になったら目が耐えられるまで読み、耐えられなくなったら読んだことを思い出し、眠りに落ちて意識が切れるまで反芻せよ。朝、目覚めたらまず、枕元にあるその本に触れ、ページを開いて読み始めよ。夕べ読んでいたところと頭の中で連結器がつながったら、起き上がって朝の支度を済まし、その後はまた読むことを再開する」
「起きている時間のすべてを読むことに捧げるのですか?」
「寝ている時もだ。たとえ宇宙の運命が変わろうとも、今手にしている一冊に注力し、目を注ぐこの一節を読むのだ。それが何語で書かれていようと、まず最初の10ページを死に物狂いで読みたまえ。分からない言葉がいくつも立ちふさがり、砂を噛むような心持ちになるだろう。しかし、その本を読むために必要な鍵は大方はそこにある。……さあ、着いたぞ」
教授は、移動書架を動かし、右隅にあった小さな本を取り、それを私に手渡しました。
「この本は?」
「私の師が独学の士に宛てて書いたものだ。読むことについて初学者が知るべき全てが書いてある。師は、尋常小学校を出て鉄道会社に給仕として入るまで、本を読んだことがなかった。上司から読み古しの小説と辞書を貰い、文字を知り読むことを知り、苦学して小学校の代用教員になり、教師をしながら学び続けて中等教員、そのあと高等教員の検定試験に合格し、第二次大戦後は、私が学んだ大学の教授となった。」
「す、すごい」
「この本の中に、こうある。『読書に別に法なし。ただ要するに煩わしき仔細のことに耐えるのみ』」
少女:すごいスパルタ! それで先生は〈本の虫〉になったのですか?
司書:残念ながら、劇的に何かが変わったわけではありません。相変わらず本を読むのは遅く、一冊読み通すのにも何度も繰り返し挫折しました。ですが、確かに変化はしていたのです。ある日、生活費が月の半ばでなくなりかけていることに気付きました。ぼんやりしていたのですが、いつのまにか本に費やす費用が増えていたのです。アルバイトを探すべきでしたが、急には見つからず、仕方なく両親に金を無心する手紙を書きました。教授との出会いについても、いくらか書いたかもしれません。
司書:まもなく現金書留が届きました。中を開けてみると、今まで入っていたことのない便箋が出てきました。父の字でした。ですが、すぐにそれは母の手紙で、父が代筆したのだということが分かりました。
「私に分かることは何でも教えてあげたけど、読むことや書くことは教えてあげられなかった。
でもきっと、おまえが知りたいと心から願うなら、おまえはちゃんと学ぶことが出来るだろう。
だから母さんは心配していないよ。
私は学校が大好きだったけど、ほとんど通うことができなかった。
それで、もうこれ以上通えないと分かったとき、そのことを先生に謝りに行ったんだよ。
先生はとても残念だと言ってくれたけど、最後にこんなことを話してくれた。
『あなたは、お母さんを助けていかなくてはならないし、弟さんや妹さんの面倒を見なきゃならないと考えて、学校へ通えないと言いに来てくれた。
だから先生はこれ以上あなたを引き止めない。でもこれだけは覚えていてね。
学ぶことはあなた一人のことじゃないの。だから我がままなんかじゃないのよ。
人は自分のためだけに学ぶんじゃないの。
それだけだったら続けてはいけない。
分からないことを覚えるのは苦しいことだし、それを考え続けるのはもつと苦しいことだから。
人はね、自分の子どもたちや孫たち、会えないかもしれない未来の人たちのためにも学ぶの。
もちろん学校の勉強のことだけじゃないわ。
お母さんやいろんな大人の人たちが、これからもいろんなことをあなたに手渡してくれるでしょう。
あなたもいつか、自分の学んだことを、次の人たちに手渡していくのよ。
困つても困らなくても、いつでも会いに来てちょうだい。
そしていつか、あなたにも手渡す人ができたら、この話をしてあげてね』」